この記事を読むのに必要な時間は約 1 分48 秒です。
ひと昔前なら、考えもしなかったことです。北海道でサツマイモが穫れる?って。
だって原産地は九州鹿児島じゃないですか。
だからサツマイモ味の「わかさいも」が生まれたんでしょう? いいじゃない、それが本当なら、北海道産のサツマイモを食べようじゃないの。
道産サツマイモ
たまたま道外客からもらった土産の大学イモを見て思いつく。「イモを使わずにイモの形と風味」を出せないか。当時道内はサツマイモの産地ではなかったのだ。
あんには大福豆(手亡(てぼう)豆)、イモのスジは昆布を活用。「引っ張ると伸びてうまくスジのように見える」。しょうゆと卵をからめて焼き、表面のつやを再現した。
当初は「やきいも」として売り出すが、胆振管内の洞爺湖温泉に移った際に姓を冠した「わかさいも」と改名し湯治客に浸透する。

90年刊行の「わかさいも一代記」の記述だ。昔と同様の材料や製法は現在も守られているという。
100年がたち、道産サツマイモはスーパーの店頭でも見かけるようになってきた。ホクレンによると昨年の生産量は前年の倍の1270トン程度となる見込みだ。
ただ全国シェアは1%未満で主産地は今も九州や関東である。
サツマイモは寒さに弱く、道内での栽培は不適とされてきた。戦中や終戦時の食料不足でも生育を試みたが産地化に至っていない。
道立総合研究機構の花・野菜技術センターによると2000年代に焼酎用栽培が始まり、その後は食用として全道各地に広まった。
農家の努力はもちろんだが気温上昇も要因だ。温暖化による予期せぬプラス効果だろう。鹿児島でサツマイモが腐る病気が流行したことも他産地の需要を高めた。
道内は主にシルクスイート、ベニアズマ、ベニハルカという品種を栽培。道外産に比べ粘りのあるしっとりした食感が特徴である。干しイモなど加工用にも向く。
寒冷地向けで高収量の新品種「ゆきこまち」も開発されて増産期待は一層高まる。サツマイモといえば北海道。100年後にはそんな時代が来るかもしれない。
(参考:北海道新聞ニュースレター)

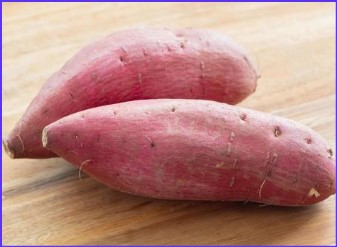


コメント